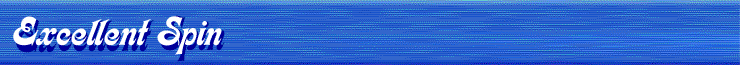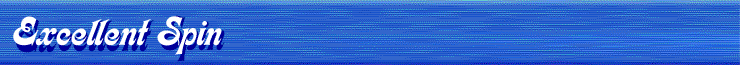|
10.新たな出会い
ユキが単身日本を立って半月が過ぎ、アメリカのコロラドスプリングスに彼女の姿があった。ユキは、スポーツ医学の病院へ通いながら、足首に負担をかけないレッスンに励んだ。もちろん、練習できないこともあったが、そんな時でも彼女はリンクに姿を見せて、他の人が練習したり、指導を受けているところを見て、ノートに書き留めていた。
そんなユキに、声をかけてきた人物がいた。韓国のキムというコーチだった。
キムは、スケート環境が整っているアメリカで、韓国の子供たちにスケートを教えるためにやってきていた。しかし、彼は国籍など関係なしに、コロラドスプリングスのリンクで彼の教えを必要としているスケーターなら誰でも分け隔てなく指導した。特に、彼自身苦労に苦労を重ねてやってきた人物であり、貧困、ケガ、差別などありとあらゆると言っていい程の逆境を跳ね除けて、フィギュアスケートを極めた指導者であった。それがゆえ、フィギュアスケートで最も大切なことと言っていいメンタルケアを得意としていた。
「ユキ、焦ってはダメだ」
「えっ、私」
「そうだ。キミのことだ。私は、キミのことは良く知っている。ソフィアのジュニアグランプリの頃からね」
「そんな、前からなんですか」
「ああ、そうだ。それから、海野コーチからキミのことも聞いている」
「そんなこと、海野コーチは一言も言っていなかったのに」
「それは、彼女が私に気を遣ってのことだと思うよ。でも、それは私のことを勘違いしているんだよ。私の仕事は、キミのように悩み苦しんでいるスケータを助けることなんだ」
「そういうことだったんですか。でも、私は焦ってなんかいませんよ。こうやって、ムリせずに練習しながら、足首の調子が悪ければ見学しながら研究を続けているわ」
「いや、そういう意味ではなく。おっと、子供たちの休憩時間が終わったので、その点については今晩、私の家に遊びに来てくれたら説明するよ。あそこにいる子供たちもいっしょだよ」
「はい。わかりました」
「こんばんは、キムコーチ」
「こんばんは、ユキ。ほら、みんな、ここにいるのがこの前ビデオで見せたユキ選手だよ」
「わあ、ホントだ。こんばんは」
「こんばんは、ユキさん、握手して」
「こんばんは、ボクも握手して」
といった具合に、そこにいる6人の子供たちが、ユキを取り囲んで握手を求めてきた。
「さあ、ユキもみんなも一緒に晩ご飯を食べよう」
「はーい。もう、お腹ペコペコだし」
「えっ、キムコーチ、私ほとんど初対面みたいなもんだし。そんな」
「全然、気にしなくていいんだよ。キミは初対面でも、私には全然初対面じゃないんだよ」
「いだだきまーす」という声がこだました。
「じゃ、私も遠慮なくいただきます」
「ところで、昼間の話ですが、私のどこに問題があるんでしょうか」
「うん、それはだね、特別私からキミに説明するものは、何もないんだよ。ただ、こうして子供たちと一緒に食事をして、一緒にスケートして、一緒に話をすることなんだよ」
「えっ。そっ、そうなんですか」
ユキは、目を白黒させた。
「まあ、そのうちにわかるさ。ここでは、そんなこと忘れて子供たちと寛いでいればいいんだよ」
翌朝、ユキは足首の調子もよく、リンクに立っていた。
軽くストレッチを行なった後、スパイラル、スピン、ステップなど足首に負担のかからない練習をしていた。
「おーい、ユキ、こっちに来ないか」
ユキが振り返ると、キムコーチが手を振っていた。
「はーい」と返事をしながら、ユキはキムコーチたちの元へ、滑り寄った
「昨日は、どうもありがとうございました。久しぶりにアットホームな一時を過ごさせていただきまいた」
「いや、こちらこそ」
「みんな、ユキ選手だよ」
「おはようございます。ユキさん」と、子供たちが声を合わせた。
「おはよう。みんな」
「ところで、ユキ。少しでいいから、子供たちにキミの滑りを教えてやってくれないか」
「えっ。私が」
「そうだ。みんな、キミのビデオを見て、どうしたら、あんな滑りができるのかと私に聞いてくるんだ。無論、ある程度教えてやることはできるんだが、練習方法などキミのやり方があって、あの完成された演技ができたはずだから」
「私でよければ、喜んで」
「はい、ユキさん、質問があります」と真っ先に手を挙げた女の子がいた。
「私は、ヨナといいます。私は、ユキさんのレイバックイナバウアをやろうとしたんだけど、全然うまくいかないの。どうすれば、できるようになるんでしょうか」
「あれを知ってるんだ。あなた、あれをやろうとしてるのね。私のをマネしようとしているのなら、それはダメよ。あれは、私が自分で考えながら作り出していったもので、今も進化し続けているのよ。より美しい形と動きを追求し、見てる人に感動してもらえることを考えてきた結果なの。だから、あなた自信にとって、美しいと思える滑りを追求してみることなのよ。それに、あれは採点項目から外れているから」
「じゃあ、私は私なりのイナバウアをやればいいんですね」
「そうよ。だけど、私から盗めるものがあれば、いくらでも盗んでもらっていいんだよ。じゃあ、一度やってみるね」
ユキは、3回転、2回転のコンビネーションから各種スパイラルから自然な形で、イナバウアを演じた後、シットスピンからレイバックスピンを演じて見せた。
「わかったわ。1つ1つの技も大事だけど、全体の流れの中で、どこで何をやるかを考えることの方が大切なことなんですね」
「そうよ。よく、わかったわね」
「私も、いつかユキさんのように滑れるようになってみせるわ。それまで楽しみにしていてね」
その会話の一部始終を聞いていたキムコーチ聞きながら何ども、頷いていた。
「さあ、二人とも、もういいかな。ユキ、他のみんなにも教えてやってよ」
「はーい。みんなお待たせ。じゃ、スピンから行くよ」
ユキはコロラドスプリングのリンクでスケートを愛する人達と時間を共にするうちに、メキメキと復調していった。
そして、半年が経ち競技会やアイスショーへも参加できるようになっていった。
しかし、ユキの足はやはり過酷なジャンプには耐えられなかった。
そんな彼女を見ていた1人のフィギュアスケーターがいた。彼は、ペアでいっしょに滑っていた最愛の恋人を交通事故でなくし、もうスケートを辞めようと思っていた。しかし、彼らの青春の全てをかけてやってきたスケートを見放すことができず、もう滑ることはできなかったが、ついついリンクを訪れ彼女と一緒に滑っていた幻影を追い求めるようになっていた。
そんな彼の視界に、転んでも転んでも、跳び続けるユキが飛び込んできた。いつしか、彼はそのリンクに頻繁に訪れ、視線でユキを追い求めるようになっていった。彼は、ユキがジャンプを跳べないのは実力ではなく、故障のせいであることを見抜いていた。
そして、とあるアシスショーで、派手なジャンプは跳びはしなかったが、あまりにも美しく舞うユキの姿を見て、再びいっしょにリンクに上がりたいという衝動にかられた。
フィギュアスケートでも特にシングルを演じるには、足首というのは生命線であった。彼は、そんなユキを見ていて、ペアやアイスダンスなら、絶対トップをはれるようになれると確信していた。
アイスショーの終わった後、手紙を添えた花束を手渡した。
ユキにとって、アイスショーは楽しいイベントであったが、終わった後の疲労は激しかった。衣装を着替えて、荷物と花束を持って帰る。アメリカで身寄りのないユキはバスで帰るしかなかった。
部屋へ帰り、眠りにつく前に、花束を花瓶に入れようとした時、手紙が溢れ落ちた。
拾い上げた手紙の内容は、シンプルだった。
「一度、ペアやってみないか。明日、キミがいつも練習しているリンクにぼくもいくから。せめて、話だけでもきいてくれ」
「なんだろうコレは。まっいいか」と思いながら眠りについた。
翌日、ユキはいつものようにリンクに立ち、ジャンプの練習をしていた。
すると、リンクの中央で派手なトリプルアクセルを繰り返す男がいた。そして、会場の注目が集まると、4回転ジャンプにチャレンジし始めた。結果はというと、全て転倒を繰り返すだけだった。しかし、何度失敗してもチャレンジし続けた。昼食の時間、彼の姿が消えた。
もう、リンクの誰も彼は帰ってこないかと思ったが、帰ってきた。そして、4回転ジャンプ&転倒を繰り返した。リンクの誰もが、彼の体はアザだらけになっていることがわかっていた。
時間が過ぎ、リンクの外は夕暮れ色に変わりつつあった。ユキには、もう彼が昨日の手紙の主であることは間違いないと思い始めていた。
その時、彼がまた派手に転倒し、立ち上がれずにいた。たまらず、ユキは彼のところに滑りよっていくと、敗れたウェアの膝から血が滲んでいた。
「あなた、何を考えているの」
「キミといっしょだよ」と言って、ニヤっと笑い、ユキを押しどけて、再び滑り始めた。
彼は、傷ついた足の調子を確かめるようにリンクを一周し、再びリンク中央でジャンプの
態勢に入った。
リンクにいる全ての人の動きが止まった。
その視線は、もちろん彼に集まっていた。
彼は、ゆっくりとした滑走から、これまでになかったような特別なバネで力強く飛び跳ねた。
なぜか、彼の動きはスローモーションビデオのように見えた。1回転、2回転、3回転、4回転完全にまわりきった。
次の瞬間氷のしぶきで彼の姿が消えた。
しぶきの中から、夕日に照らされた彼の姿が現れた。
静まり返ったリンクに彼の滑走音のみが響いた。
そして、リンクは割れんばかりの拍手に包まれた。
彼は、そのままユキの目の前までやってきた。
「不器用なオレだけど、ペアやってみないか、名前はボールドウィンっていうんだ」
「あんたも、むちゃくちゃね。私といっしょで」と、言いながらユキは、膝まづいたボールドウィンに手を差し伸べた。
ほとんどの演技は復調していたユキではあったが、どうしてもトリプルルッツやトリプルフリップなど難易度の高い3回転ジャンプに限界を感じていたユキは、ボールドウィンの熱意に押されて、ペアをやってみようという気になった。
「明日から、オレはこのリンクに通うよ。悪いが、ペアではオレの方が先輩だ。オレの言うことを聞いてもらうよ」
「わかったわ。ボールドウィン先輩」と、ユキはニコっと笑った。
次の日から、ユキとボールドウィンの猛練習が始まった。当初、ユキにとって戸惑う局面も多かったが、元々ペアに要求されるしなやかさの天性を開花させ、1ヶ月あまりの練習を積んでエントリーしたローカルの競技会を総ナメにし始めていった。
そして、2ヶ月が経ち、とある全米選手権の大会で遂に優勝を果たした。短い期間ではあるが苦難を共にしてきたボールドウィンとも喜びを分かち合うことができた。
優勝直後、かつてボールドウィンとペアを組み恋人でもあった彼女の妹も涙を流して喜びを伝えにきた。ユキには、その涙が単に姉の夢を果たしてくれたという以上の意味があることを感じられた。ボールドウィンも、死に別れた彼女の面影を忘れるために彼女の妹を避け、スケーターである妹のペアのオファーを断っていた。しかし、妹の涙が彼女との思い出を洗い流してしまおうとしていることを強く感じた。それは、ユキの気持ちがこれ以上ボールドウィンへ傾くことを恐れるとともに、この大会で活躍しているシングルの選手たちへの闘争心へとつながっていった。
表彰式とエキシビジョンが終わり、着替え終わったユキとボールドウィンはロビーで二人きりになった。
「ボールドウィン、私はあなたに告げなければならないことがあるの」
「えっ、なんだい。急にあらたまって」
「ごめんなさい。これまで、ペアに没頭してきたつもりだったんだけど、やっぱり私・・・」
「今さら何を言ってるんだ。キミの気持ちもよくわかるんだけど、ペアのすばらしさもキミに伝え、キミもやっと昇り調子になってきたところじゃないか」
「ペアのすばらしさは十分理解したつもりだわ。だけど・・・、少し考えさせて。練習は続けさせてもらおうと思っているし」
「ダメだ。そんな気持ちでペアは組めないよ。ペアは、気持ちの乱れがあると危険なのは、ユキもわかっているだろ。どっちにしろ、ユキの気持ちの整理がつくまで待っているし、ユキがシングルへ戻るのなら、新しいペアを探すつもりだし。オレは、ユキのおかげで死に別れた恋人とスケートを切り離して考えられるようになった。ユキも、自分の気持ちに正直な方向を目指してほしいんだ」
「オレは、明日から隣町にある地元のスケート場で練習しているよ。気持ちの整理が着いたら、おいで」と言い残して、ボールドウィンは去っていった。
ボールドウィンとの出会いから、まだわずか3ヵ月程しか経っていなかったが、一人残されたユキの目からは、なぜかとめどなく涙が溢れ出した。
次の日からユキは、また1人で練習に励む日々が始まった。しかし、コロラドスプリングスのリンクには、キムコーチや子供たちがいた。キムコーチは、ユキの心を全て見透かした様に彼らの輪の中にユキを迎え入れてくれた。
数日が経ったある夜、みんな練習を終えてスケート場のロビーでテレビに釘付けになっていた。
テレビには、ちょうど4年に1度のオリンピックの映像が映し出されていた。
足のケガさえなかったら、このオリンピックに出ることができたかもしれないという思いが過ぎったが、自分自身でその思考回路を断ち切り、世界の強豪達の演技に釘付けになっていった。
そして、その時点で、トップスケーターにはい上がった新井の演技が始まった。
リンクの観客、テレビを見ている全ての視聴者が彼女の演技に釘付けとなっていた。そして、演技が架橋に入ると、新井がセールスポイントにしているレイバックイナバウアで、
場内は一瞬静まり返った。ほとんど、全世界でテレビを見ていた視聴者もそうであったが、
横でいっしょに見ていたヨナが、「あれはユキの」と言った時点で、ユキが彼女の言葉を遮って、「しっ」と人差し指を唇に当てた。
それでもヨナは、よほど悔しかったのか、「ユキが、もしダメでも、私が必ず世界一になってレイバックイナバウアを演じて、ユキがあみ出したもので、今でもユキがレイバックイナバウアNo1だと、世界中に公表するわ」と言った。
ユキは、苦笑いしながら、「そんなことは、どうでもいいことなのよ」と言った。
しかし、ユキの中では沸ふつと闘争心のような熱い気持ちがこみ上げていた。
「殴り込みをかけよう」と。
翌日、ユキは隣町のスケート場を訪れた。
「ユキ、吹っ切れたようだな」
「はい」
「オレも、これまで断っていた彼女の妹とペアを組むよ」
「運がよければ、ソチで会いましょう」
ユキは、アメリカで、できる限りのリハビリとレッスンを積んだ。アメリカにいても、もうこれ以上回復することはない。もう、トリプルルッツジャンプやトリプルフリップジャンプを演技に取り入れることはできないこともわかっていた。
こんな状態で、ゴールドメダリストを産み出した全日本へ殴り込みをかけるなど、正気の沙汰でないことは本人が一番わかっていた。
しかし、全日本で置き忘れてきた何かを取り戻すために、ユキはどうしても今日本へ帰るしかなかった。
|